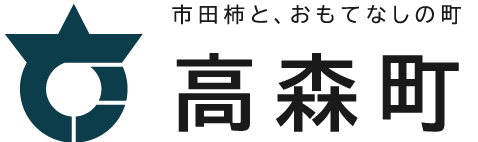6月11日(水曜日)に開催された「まちづくり講演会」には多くの方のご参加をいただき、ありがとうございました。
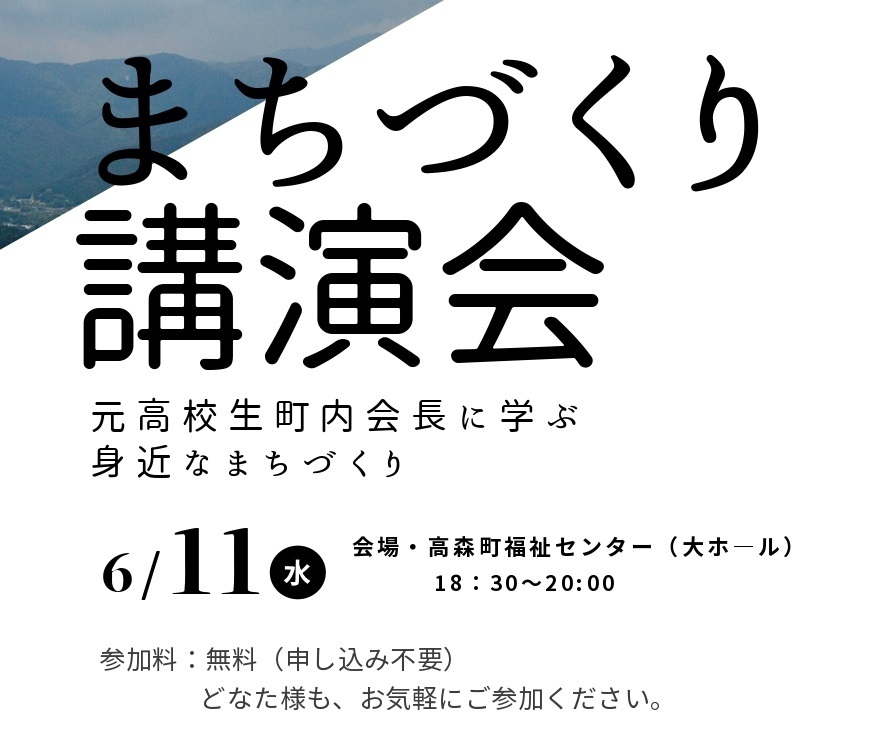
講演会当日のいただいた質問に対し、講師の金子様から回答をいただきましたので、共有させていただきます。
Q1: 年寄り(古い考えの強い人)との話をどの様にしたのか?
A:その方の思いや考え方に寄り添いながら話を聞き、どの部分を大切にしているのかなど、表面的な言葉だけでなく、言葉の背景となっているような出来事や歴史を深く知ることを意識しました。
Q2: 50世帯→300世帯(自治会)、1000世帯(区)への解決の道筋
A:加入世帯数を増やしていくにはどうすればいいのかという質問でしたら、まずは活動や組織を知ってもらうことが大切だと活動を通して感じました。
私の地域でも、未加入世帯の方々の多くは関心がなかったり、知らなかったりなどが多かったです。
いきなり世帯数を増やすのは難しいかもしれませんが、知ってもらう過程はとても大切だと思います。
Q3: 町内会長を経験され、町内の方は楽しく町内会のことに関わりを持てる方が増えたと感じられているのでしょうか。
A:私は増えたと感じています。行事や活動に少しずつではありましたが人が増えたと思います。
また、私自身も会長という役職を通して、今まで関心があまりなかった地域の事などに興味を持ち、地域の今まで知らなかった方々との交流はとても魅力的なものでした。
Q4: 例えばお祭りの「そもそも大切なこと」はどのレベルまで掘り下げたのか。また、町内会長の後任者決定のプロセスはどうだったか。
A:この活動は何のために誰のために行っているのかというところまで掘り下げました。
コロナの時期ということもあり、活動の継続や存在までもが議論される中で、今一度、何が大切なのかを考えました。
後任の決定は今まで同様に輪番制という形で役員を決定しましたが、若い子育て世代の方が引き受けてくださいました。
Q5: 今、個人情報が取れない時代です。それらを変えるのはどうか?(あまりしゃべりたがらない)
A:今の時代、個人情報の扱いはとても難しいです。
私もたくさん悩みましたが、今までと同じように全ての人の情報を集めるのではなく、町内会として把握しなければならない情報(避難際、手助けが必要な方など)をしっかりと集めることにしました。
Q6: 町内会費ってどれくらい
A:年間3000円ほどです。
Q7: 一番大事な「我が事」(自分事)にするところがキーポイントですが、「LET」を目的にしていく事でしょうか。
A:我が事になる過程は人によって様々ですが、組織としてLETは活動していく上でとても大切な考え方だと思っています。
LET(※)の考え方を軸に様々な方がかかわりやすい組織作りをしていくことが大切だと思います。
※LETは下記の言葉の頭文字です。
L…LOVE 他社の喜びは、自分の喜び
E…ENJOY みんなが楽しめるような活動
T…THANKS 様々なものや人に感謝の心
Q8: 高校生←子どものころからこういったことを思っていたのか
A:私の学生時代は地域活動や地域の人とのコミュニケーションに対して、あまり関心がありませんでした。
しかし、とあるきっかけで地域に触れる機会がありそこから少しずつ考え方が変わっていったと思います。
Q9: 町内会の加入率が低下すると困ることは何ですか
A:加入率が下がると、町内会が地域の代表として機能しにくくなります。例えば、行政に道路の補修や災害対策などの要望を出す際、加入率100%の町内会の意見と、加入率30%の町内会の意見とでは、その重みや説得力が異なってくる場合があります。
また、町内会は、行政からの連絡事項(ゴミ出しルールの変更、防災訓練のお知らせなど)を住民に伝える役割も担っています。
加入率が低いと、非加入者への情報伝達が難しくなり、地域全体で情報が共有されにくくなる恐れがあります。
Q10: 町内会長になったことを友人などに伝えたとき、どんな反応だったか
A:みんな驚いていました。それと合わせて「頑張ってね」など前向きな言葉をもらったのを覚えています。
Q11: 高校生や中学生、小学生など、子どもに関心を持ってもらうにはどうすればよいと思うか
A:子どもたちが楽しめるような行事を行ったり、また子どもたちの意見を運営に取り入れてみたりなど、「町内会は楽しいことをしている」「自分たちの意見を聞いてくれる」というイメージを持ってもらうことが、子どもたちの関心を引き出す第一歩だと思います
Q12: 金子氏の退任後、次期会長以降の現在の町内会の様子を聞きたい
A:現在直接運営にかかわっているわけではないので詳細は分かりませんが、回覧などを拝見し、しっかりと活動を行っているのをよく目にします。
Q13: 大学発ベンチャー企業をどのように立ち上げたのですか(方法、資金、収支等お答えできる範囲で)
A:大学発ベンチャーを立ち上げたというより、もともと立ち上げた会社が大学発ベンチャーの認定を頂いた形になります。
Q14: 多様な価値観がある中で、地域住民の興味関心をどのように高めていったか。
A:いくつかキーワードを上げますと、「参加のハードルを下げる」「一人一人のできることや得意な事で関わってもらう」「活動の可視化を行う」。
このような取り組みが多くの方々が関わりやすい仕組みだと思い実行しました。