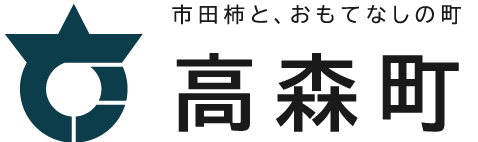気候変動適応計画の策定の経緯
気候変動(温暖化やそれらによる影響)が地球全体に様々な影響を及ぼす中、当町特産品である市田柿にも深刻な影響が出始めています。
気候変動に対しどのような対策を実施しても、将来の気温上昇は避けることはできない見込みです。そのため気候変動に備える対策、「適応策」の整備が急がれています。
高森町と法政大学は2017年に事業協力の協定を締結し「市田柿の気候変動対策」の研究を進めています。この協定により3年間かけて、市田柿の気候変動への適応計画を策定してきました。
今年の8月に地域の農家や住民とともに検討を重ねた計画がまとまりました。
「気候変動の市田柿への影響と適応策に関する研究」について法政大学と協定を締結しました
市田柿の適応策計画の内容
これまでのアンケートやワークショップにて出されたアイディアは、「柿の栽培・加工技術の改善」、「生産・経営形態の改善」、「市田柿を活かす新たな地域づくり」の3つに分類されました。
柿を生産される農家はもとより、公的技術開発機関、行政がそれぞれに役割を持ち、連携して地域ぐるみで一丸となって対策を進めることを目標としてあります。
「柿の栽培・加工技術の改善」については、「従来の栽培技術の改善」及び「革新的な栽培技術」、「革新的な加工技術」の開発を、農業試験場などの専門機関が主導して実施をすることとします。「技術の蓄積・共有」については、町や県などが連携し、率先して進めることとしました。
「生産・経営形態の改善」については、「会社組織あるいは農家間の連携により共同加工・共同経営・共同出荷」を進める。また、商品を買ってもらえるための検討に余地があるため、「より買ってもらいやすい商品開発」を優先的に進めることとしました。
「市田柿を活かす地域づくり」については、将来的な市田柿生産のすそ野を拡大するために、より多くの人に高森町に来てもらい、市田柿に触れてもらう機会を作ることが重要とのことです。そのため「高森に来て、食べてもらう工夫」を優先的に実施することです。また、若者さらには退職者も含めた新規参入者への支援という意味で、「若手生産者への支援など」を優先的に実施します。
「将来の気候変動を見通した市田柿の気候変動適応策計画」 (PDF 1.05MB)


市田柿ワークショップ風景 これまでの活動 その1

市田柿ワークショップ風景 これまでの活動 その2