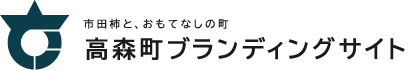市田柿の誕生まで
柿は奈良時代に中国から渡ってきたと言われています。江戸時代には飯田下伊那地方でも柿が作られていました。
当時の飯田下伊那を代表する柿は「立石柿」。江戸でも大変有名でした。伊勢信仰が盛んだった下市田村(現高森町下市田)に立てられた伊勢社の境内にあった柿の古木は「焼いて食べても美味しい」と評判で「焼柿」と呼ばれていました。
この伊勢屋敷に住んでいた寺子屋の師匠 児島礼順が、柿を育て食べることを奨励し、この柿は接木によって村中に、そして村外へと広がりました。
明治時代末期には、市田柿の商品化が進められ、また数々の偉大な先人によって戦後には「市田柿」として東京や名古屋の市場進出を果たすまでになりました。
そして、平成18年に特許庁より「地域商標登録」として認定され、今日の市田柿があります。
書籍『市田柿のふるさと』
2006年(平成18)年10月27日、特許庁により全国52件の一つとして当町の特産品『市田柿』が「地域ブランド(地域団体商標)」に認定されたのを受け、2006年12月20日に郷土歴史家、柿生産者、町議会議員、地元役員、役場職員等14名からなる「市田柿の由来研究委員会」が発足しました。この方々の手によって、当町の特産品「市田柿」の由来についてまとめた書籍『市田柿のふるさと』が作られました。
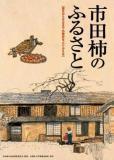
▼PDFデータはこちら▼
市田柿のふるさと (PDF 13.3MB)
販売について
限定300部、1冊500円で高森町役場2階産業課・高森町歴史民俗資料館「時の駅」で販売中です。(残りわずかとなりました。)
(1)役場から発行される納付書にて金融機関等でお支払下さい。入金の際の手数料等はご購入者様の負担でお願い致します。
(2)お渡しする方法として、「1.役場まで直接取りに来てもらう」又は「2.役場から、着払いで送る」の2通りがございます。
数量に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。ご了承下さい。
『市田柿のふるさと』が完成するまで
市田柿の由来研究委員会の発足
2006(平成18)年10月27日、特許庁により全国52件の一つとして当町の特産品『市田柿』が「地域ブランド(地域団体商標)」に認定されたのを受け、2006年12月20日に郷土歴史家、柿生産者、町議会議員、地元役員、役場職員等14名からなる「市田柿の由来研究委員会」が発足しました。
この委員会は「地域ブランドとして認定された当町が発祥地とされる『市田柿』の歴史を紐解き、その研究成果を後世に伝えると共に町の活性化に繋げていく」ことを目的として、約2年間をかけ資料等を収集・研究し、その由来等を明らかしてきました。
書籍の発行の経過
平成20年1月8日には北沢会長より町長へ「市田柿を活用したまちづくりへの提言」が提出され、町ではこの提言書を元に、平成20年度事業として市田柿の由来をまとめた本を発行する事業を進めてきました。
書籍発行の目的等について
事業費に関しては、長野県の「元気づくり支援金」に採用され、事業費1,470,000円を県からの補助でまかなうことができました。A4サイズで52ページ、文章のみならず写真やイラスト等を効果的に使った「読みやすい」本をコンセプトに進めてきました。取材の中から浮き出してきた、これからの市田柿の未来についての課題等も提起し、生産者の皆さんが抱えている悩み等を明らかにすることも試みています。地域ブランドになったと共に多くの悩みを抱える生産者の方々を少しでもバックアップできるように、そしてこの書籍が市田柿が本来持つ「味」「こだわり」「栄養」「風景」などの「ブランド力」(付加価値)を更に高めるツールの一つとして、積極的に活用されることを期待しています。また、生産者のみならず南信州に住む人々が、自らが住む地域の素晴らしい資源の可能性を再認識することを望んでいます。