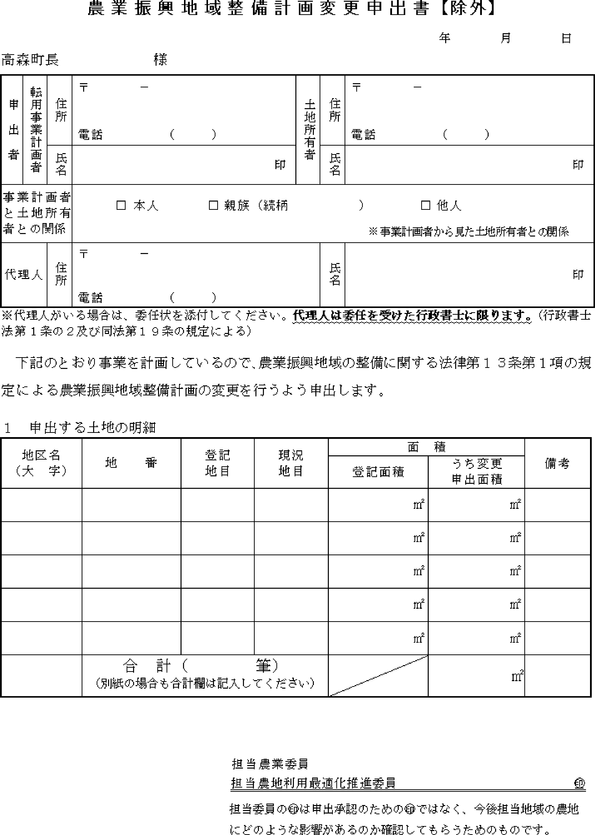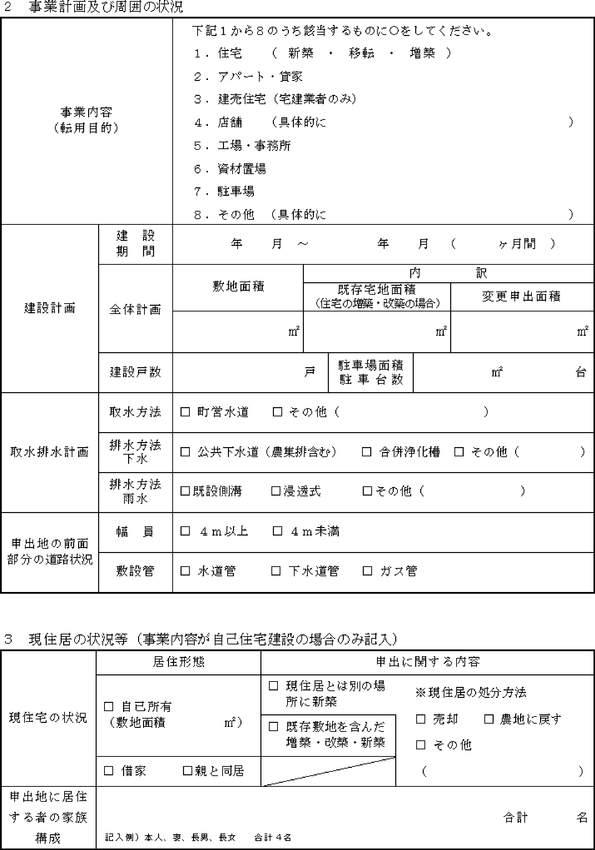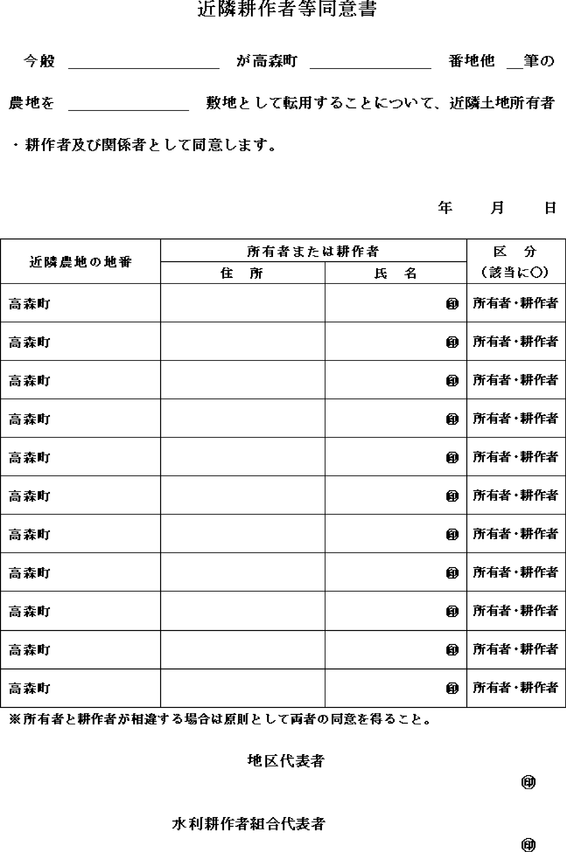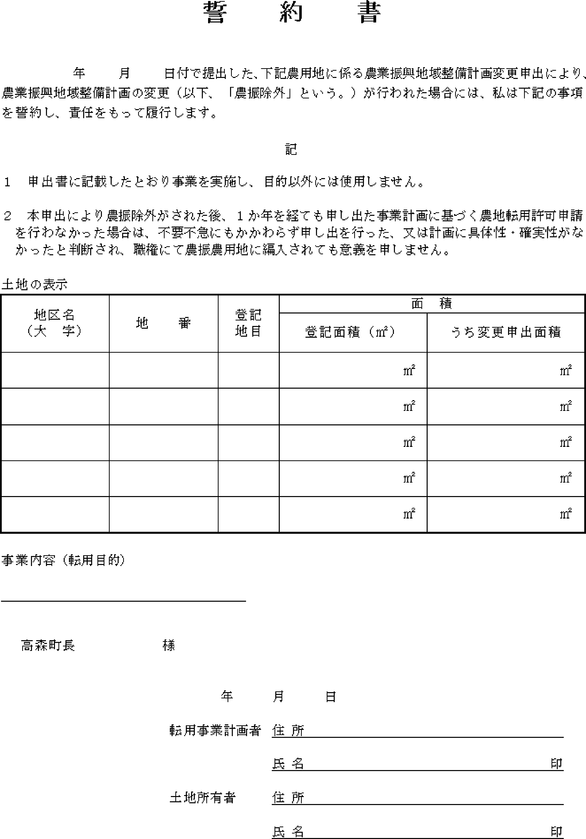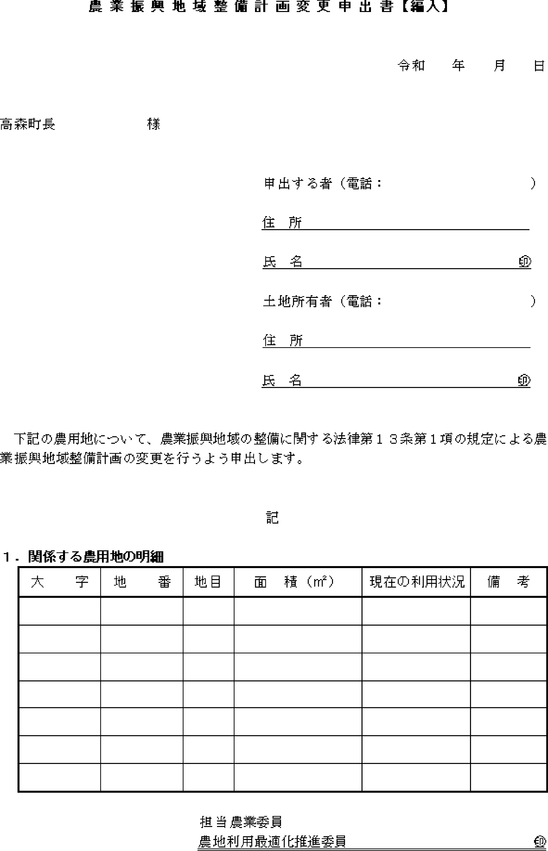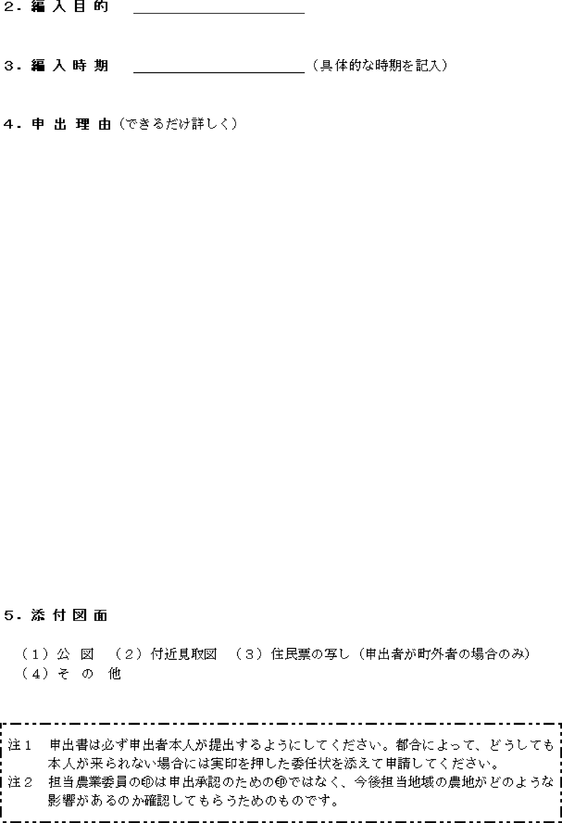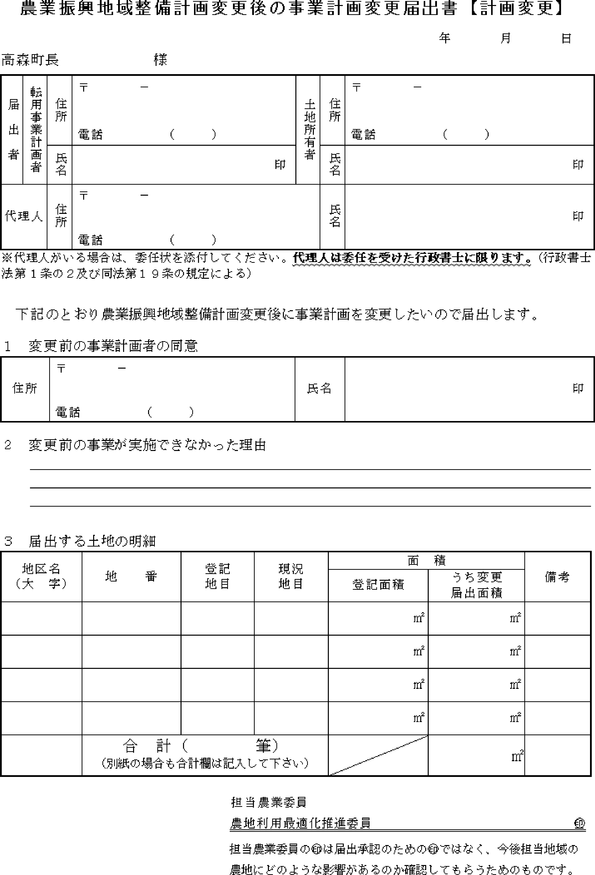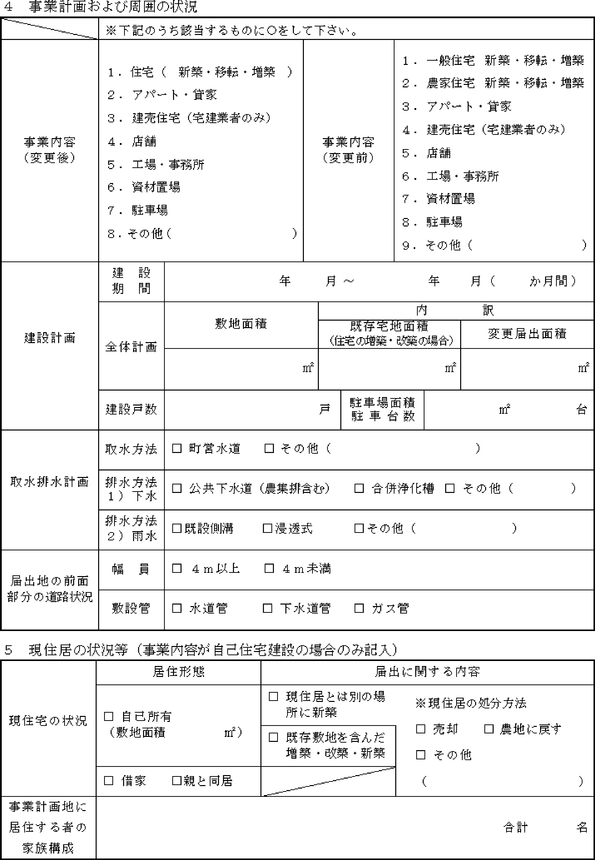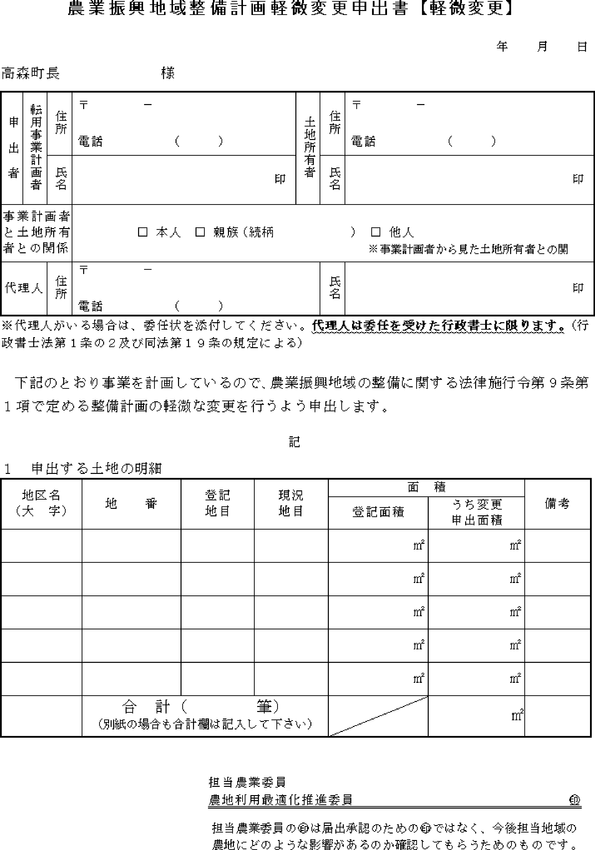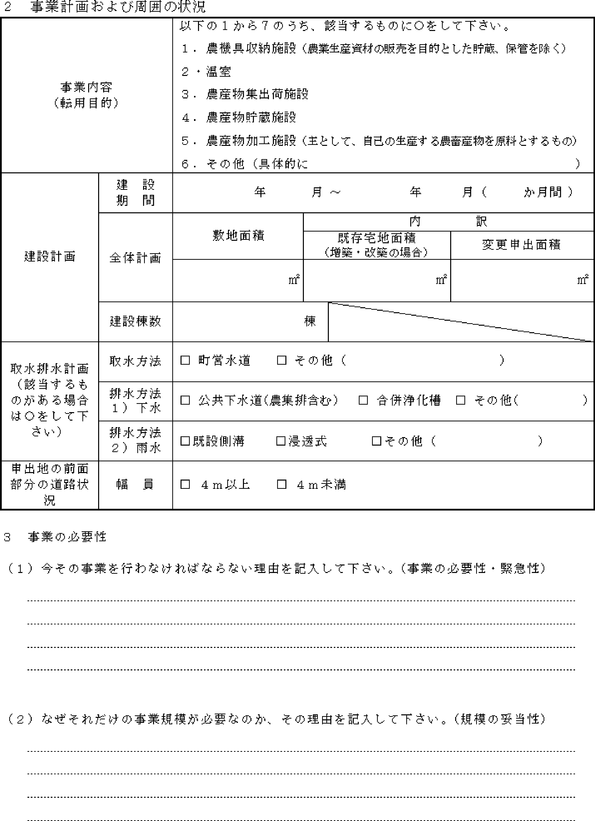○高森町農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱
平成23年3月31日要綱第4号
高森町農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条の規定に基づく高森町農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)のうち、同法第13条による変更時の取扱いを定めることにより、整備計画の適正な管理運営に資することを目的とする。
(整備計画の部分見直し(随時変更))
第2条 町長は、経済事情の変動その他情勢の推移を勘案し、整備計画について次の事項について部分見直しを行う。
(1) 農地転用(以下「転用」という。)事案に係る農用地区域からの除外
(2) 農用地区域への編入
(3) 軽微な変更
(4) 公共公用施設用地区域に係る農用地区域からの除外
(転用事案に係る農用地区域からの除外(第2条第1号の随時変更))
第3条 申出者及び土地所有者(以下「申出者等」という。)は、事業計画のために農用地区域内の土地について農用地区域からの除外が行われる必要がある場合、農業振興地域整備計画変更申出書【除外】(様式第1号。以下「除外申出書」という。)により、町長に申出する。
2 申出者等は、除外申出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 理由書(様式第2号)
(2) 土地選定経過書(様式第3号)
(3) 近隣耕作者等同意書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 申出する土地の登記事項全部証明書
(6) 位置図
(7) 付近見取図(住宅地図)
(8) 公図
(9) 建物等の設計図
(10) 敷地内配置図面
(11) 住民票の写し(申出する者が町外者の場合のみ)
(12) その他町長が判断に必要とする書類
3 町長は、申出書を参考として、次の事項の要件を全て満たしているか確認し、整備計画の変更の可否について決定する。
(1) 除外する緊急性及び必要性があること。(転用後の土地利用については具体的な計画が必要であり、宅地分譲はこれに該当しないので認めない)
(2) 農用地区域以外に代替すべき土地がないものであること。(当該用途の通常の利用形態を参考に当該土地が必要であるのか、又はその規模が適当であるのかを判断する。)(農振法第13条第2項第1号関係)
(3) 農用地区域内における農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。(集団的農用地の中央部に他用途の土地が介在することにより、高性能機械による営農や効果的な病害虫防除等に支障が生ずる場合及び小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業や農地流動化施策への支障が生ずる場合等)(農振法第13条第2項第2号関係)
(4) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者等の担い手)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。(農振法第13条第2項第3号関係)
(5) 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。(ため池、排水路、土留工、防風林等の農用地区域内の土地の保全上必要な施設について、その損傷により、土砂の流出又は崩壊、洪水、たん水、飛砂、地盤沈下等の災害の発生が予想されるとき、農業用排水施設等の農用地区域内の土地の利用上必要な施設について、土砂等の流入による用排水停滞、汚濁水の流入等が予想されるとき等)(農振法第13条第2項第4号関係)
(6) 当該変更に係る土地が土地改良事業等の施行に係る区域内の土地に該当する場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。(「工事が完了した年度」とは、工事完了公告における工事完了の日の属する年度。(農振法第13条第2項第5号及び農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号、以下「農振法施行令」という。)第8条関係))
(7) 除外後、以下に該当し農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用の許可を受けられると見込まれること。
ア 第1種農用地区域内の場合、不許可の例外に該当すること。
イ その他農地法の規制対象でないこと。
(8) 複数隣接する建売住宅を転用目的としている場合、合計面積が2,000㎡以内であること。
(9) 担当農業委員が農地転用による影響について確認していること。
(10) 地区代表者、水利耕作者組合代表者及び近隣農用地の耕作者並びに土地所有者(以下「近隣耕作者等」という。)の同意があること。なお、近隣耕作者等の土地と近隣耕作者の土地の間に、農道又は水路があり、それらが幅4m以上である場合は当該耕作者の同意は必要ない。
(農用地区域への編入(第2条第2項の随時変更))
第4条 申出者等は、農用地を農用地区域への編入が必要である場合、農業振興地域整備計画変更申出書【編入】(様式第6号。以下「編入申出書」という。)により、町長に申出する。
2 申出者等は、編入申出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 申出する土地の登記事項全部証明書
(2) 位置図
(3) 付近見取図(住宅地図)
(4) 公図
(5) 住民票の写し(申出する者が町外者の場合のみ)
(6) その他町長が判断に必要とする書類
(整備計画変更後の事業計画変更)
第5条 申出者等は、第3条の除外申出書による整備計画の変更後、当該除外申出書に係る事業計画に変更が生じた場合、農業振興地域整備計画変更後の事業計画変更届出書(様式第7号。以下「事業計画変更届出書」という。)により、町長に届出する。
2 届出者等は、事業計画変更届出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 近隣耕作者等同意書(様式第4号)
(2) 申出する土地の登記事項全部証明書
(3) 位置図
(4) 付近見取図(住宅地図)
(5) 公図
(6) 建物等の設計図
(7) 敷地内配置図面
(8) 住民票の写し(届出する者が町外者の場合のみ)
(9) その他町長が必要とする書類
3 町長は、第1項の届出を受付たときは、その届出について受理書を交付する。
(申出書等の受付期間)
第6条 第3条から第4条までの申出書の受付は、毎年2月、6月、10月の年3回とし、受付期間は当該月の開庁日とする。ただし、国及び地方公共団体が行う事業並びに町長が特に必要かつ緊急を要すると認めた事業に係るものにあっては、その都度指定する期日までに提出するものとする。
2 前条の届出書及び第9条の申出書の受付は、毎月15日締めで随時行うものとする。ただし、15日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、それぞれその前日とする。
(高森町農業振興地域整備促進協議会への諮問)
第7条 町長は、第3条及び第4条の申出について高森町農業振興地域整備促進協議会に諮問する。
(農業振興地域整備計画変更の事務処理)
第8条 第3条及び第4条の申出について町長は整備計画変更案を策定し、農振法及び長野県の「市町村農業振興地域整備計画の変更に係る事務取扱要領」に基づく事務処理を行う。
2 町長は、整備計画変更案について県からの同意を得て(農振法第8条第4項)、整備計画の変更を行い、同時に以下のとおり通知等をする。
(1) 申出に沿う整備計画の変更を行う場合には、申出者及び土地所有者にその旨通知する。
(2) 申出に沿う整備計画の変更を行わない場合又は県が同意しない場合には、申出者及び土地所有者に対し速やかにその理由を付した文書により回答する。
(軽微な変更(第2条第3号の随時変更))
第9条 申出者等は、農振法施行令第10条第1項で定める農用地区域内の土地を農業用施設の用に供する等の軽微な変更の必要がある場合、農業振興地域整備計画軽微変更申出書(様式第8号。以下「軽微変更申出書」という。)により、町長に申出する。
2 申出者等は軽微変更申出書に次の各号に掲げるものを添付する。
(1) 近隣耕作者等同意書(様式第4号)
(2) 申出する土地の登記事項全部証明書
(3) 付近見取図(住宅地図)
(4) 公図
(5) 建物等の設計図
(6) 敷地内配置図面
(7) 住民票の写し(申出者が町外者の場合のみ)
(8) その他町長が判断に必要とする書類
3 町長は、整備計画を変更する場合、農振法第12条の公告縦覧を行い、同時に申出者等に通知をする。変更を行わない場合、申出者等に対し速やかにその理由を付した文書により回答する。
(申出の取下げ)
第10条 第3条から第5条、前条の申出後に取下げの必要が生じた場合、農業振興地域整備計画変更申出取下書(様式第9号)を町長へ提出すること。
(農用地区域への再編入)
第11条 町長は、次の場合、申出を参考として変更した農地を再度農用地区域に編入することができる。
(1) 申出書に故意による嘘偽の記載があると認められる場合
(2) 転用事案に係る農用地区域からの除外後、農地転用手続きが行われない等事業の緊急性及び必要性が認められない場合
附 則
この要綱は、平成23年3月25日から施行する。
附 則(平成25年3月25日要綱第4号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。